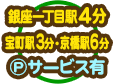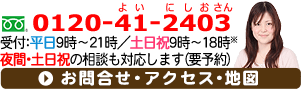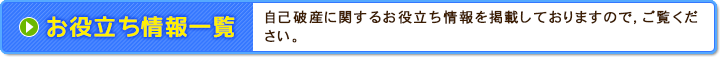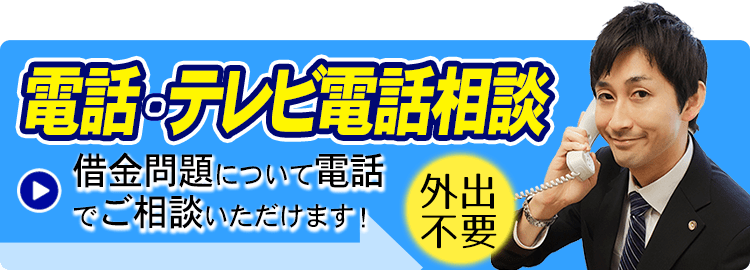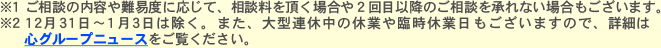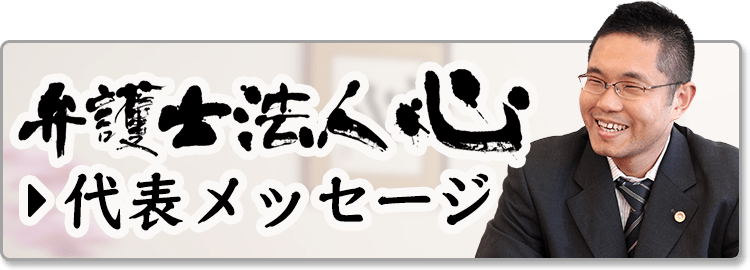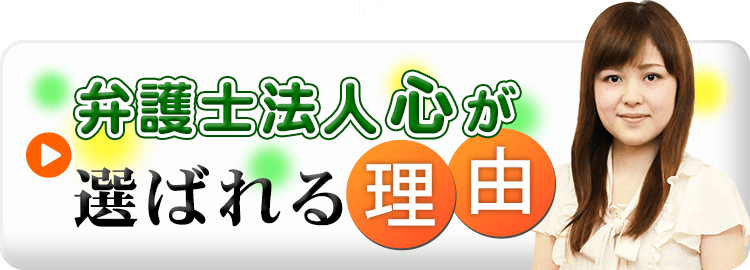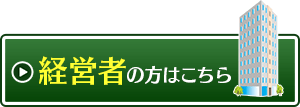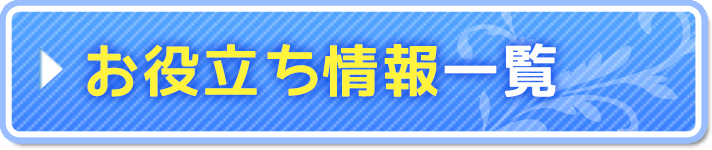Q&A
亡くなった親名義の家に住んでいる場合自己破産するとどうなりますか?
1 自己破産をすると、亡くなった親名義の家は原則として換価される
結論から申し上げますと、親がなくなり、遺産分割が未了の状態で親名義のままになっている家や、相続人が債務者の方のみであり単に相続登記をしていないという場合には、自己破産をすると親名義の家は換価の対象となります。
自己破産は、原則として債務者の方の財産を破産管財人が売却し、売却して得られた金銭を債権者への返済に充て、返済しきれなかった部分については免責されるという手続きであるためです。
遺産分割が未了である場合、債務者の方は法定相続割合に相当する共有持ち分を持っていることになりますので、自己破産手続きの開始後、破産管財人が遺産分割協議を行い、債務者の方の共有持ち分を売却・換価することになります。
相続人が債務者の方のみである場合には、親名義の家の所有者は債務者の方のみとなりますので、やはり自己破産手続きにおいて破産管財人が売却・換価をします。
2 遺産分割協議をしていた場合
すでに遺産分割協議をしているが、相続登記が未了であったため、家が親名義のままであったという場合は、状況が複雑になります。
まず、遺産分割協議をし、債務者の方が親名義の家を取得していた場合には、自己破産手続きにおいて換価の対象となると考えられます。
次に、遺産分割協議をし、他の相続人の方が親名義の家を取得したといえるものの、相続登記をしていなかったという場合については、判断が分かれていると考えられます。
実務上、相続人間では被相続人の配偶者(亡くなっていない方の債務者の方の親)が被相続人の家を引き継ぐ旨の同意がなされ、被相続人の配偶者が固定資産税の支払いを行っており、相続人全員が、被相続人の名義の家の所有者が被相続人の配偶者であると思っているケースは多く見受けられます。
このような場合、債務者の方から見ると被相続人の配偶者が家の所有者であることから、自己破産をしても家は換価されないと考えられます。
しかし、相続登記がなされておらず、かつ遺産分割協議を完了していることを客観的に示すものがない場合、裁判所や破産管財人から見ると、遺産分割未了とも考えられます。
そのため、債権者保護の観点からも、遺産分割未了として扱い、債務者の方の法定相続割合に相当する持ち分を換価の対象とすると考える傾向にあります。
このような場合、固定資産税の請求先となっている相続人代表者が被相続人の配偶者と指定されていることや、実際に被相続人の配偶者が固定資産税を支払っていること、そのほか被相続人の配偶者が家を取得したと言えるような相続人間のやり取りなどを説明することで、自己破産をした際に換価の対象から外すよう働きかけるという方法が考えられます。
ただし、必ずしも親名義の家を換価の対象から外せるとは限らないので注意が必要です。
自己破産の免責決定通知はいつ届きますか? 同時廃止の場合、どのくらいの期間がかかりますか?